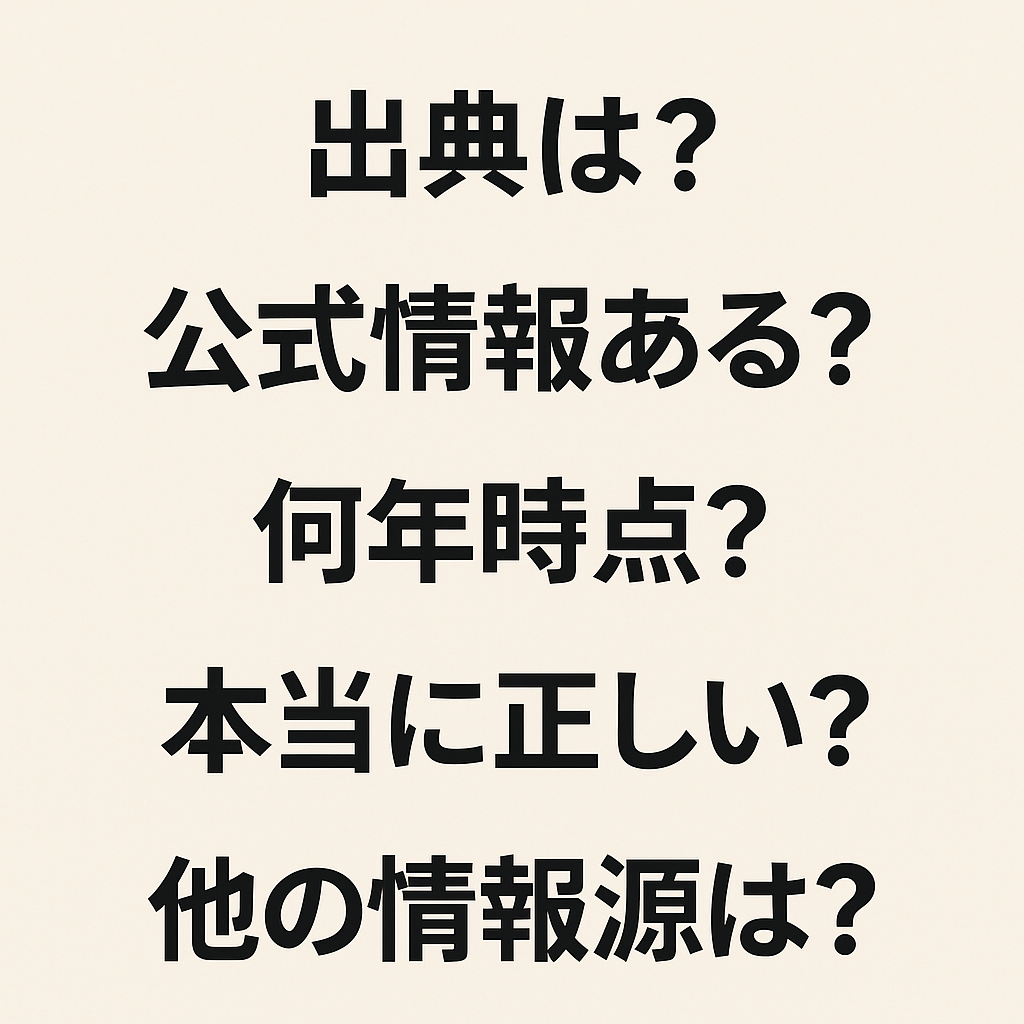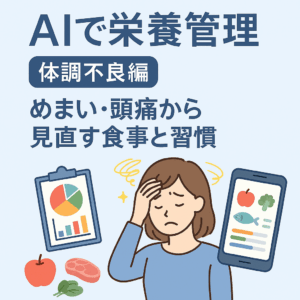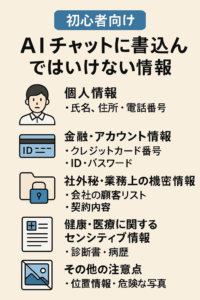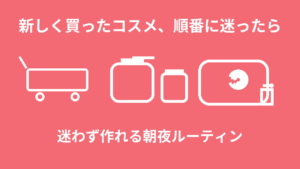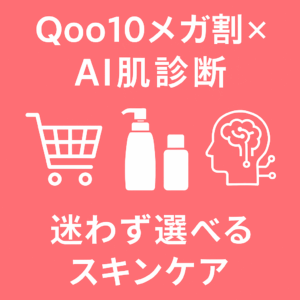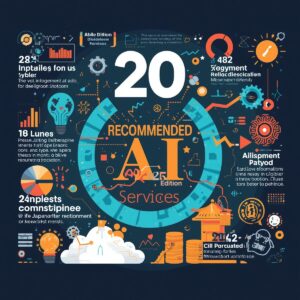はじめに
「AIは間違っていることを言うから使わない」――よく耳にする意見です。
確かにAIの回答は万能ではなく、誤った情報や不完全な内容が含まれることがあります。
しかし、それを理由にまったく使わないのは大きな損失です。
AIは 「正解を与えてくれる先生」ではなく、「一緒に考えるアシスタント」 だからです。
本記事では、AIを “鵜呑みにせずに上手く活用するコツ” を紹介し、実際のファクトチェック事例や質問例も取り上げます。
AIを活用する5つのコツ
1. 下書きツールとして使う
AIが出した答えを最終形と思わず、「たたき台」として利用するのが基本です。
- 文章の構成を考える
- アイデアを広げる
- 表や箇条書きで整理する
👉 最終的な仕上げや正確性の確認は、必ず自分で行いましょう。
2. 複数の回答を比較する
AIは質問の仕方によって答えが変わることがあります。
- 同じ質問を2〜3回してみる
- 別のAIサービスと比較する
👉 比較することで「偏った誤り」に気づきやすくなります。
3. ファクトチェックを行う
数字や専門情報は特に 裏取りが必須 です。
- AIの答えを「検索ワード」としてGoogleで調べる
- 出典や日付が明示されているか確認する
- 複数の情報源で一致しているかを確かめる
👉 AIの答えをそのまま信じるのではなく、調べるヒントとして活用する のがポイントです。
4. 間違ってはいけない分野は公式を確認
以下の分野は、必ず公式情報を最終確認しましょう。
- 医療・健康(診断や薬の情報)
- 法律・税金・契約関連
- 投資や金融商品
- 行政手続きや選挙情報
👉 厚生労働省・国税庁・金融庁・自治体サイトなど、公式が最終判断材料 です。
5. 【事例】AIの答えをファクトチェックしてみた
ケース:確定申告の期限
AIに「日本の確定申告の提出期限はいつ?」と質問したとします。
- AIの回答例
「日本の確定申告は3月31日までに提出が必要です」 - 公式情報(国税庁サイト)
実際には「翌年の2月16日から3月15日まで」が原則的な期限。
※年によって休日と重なる場合は翌平日まで延長される。
👉 一見正しそうでも誤りがあります。AIの答えをそのまま検索ワードに使うと、すぐに国税庁公式ページへたどり着けます。
ファクトチェック質問例
詳しく確認したいとき
- この情報の根拠となる公式サイトや出典を教えてください
- この回答は何年時点の情報ですか?
- 複数の情報源を比較して一覧にしてください
- 国税庁(厚生労働省など)の公式情報をもとに答えてください
- 誤っている可能性がある場合は注意点も書いてください
一言でサッと聞きたいとき
- 出典は?
- 公式情報ある?
- 何年時点?
- 本当に正しい?
- 他の情報源は?
👉 一言レベルでサッと確認し、必要なら深掘りするのが効率的です。
まとめ
AIは確かに間違うことがあります。
しかし「間違うから使わない」のではなく、「間違う前提でどう使うか」 が大切です。
- 下書きやアイデア出しに使う
- 複数回答を比較する
- ファクトチェックを必ず行う
- 間違ってはいけない分野は公式を参照する
- 一言質問でサッと確認 → 必要に応じて深掘り
こうしたポイントを押さえれば、AIは強力な相棒になります。
間違いを恐れるより、補助輪として上手に活用する発想 を持ちましょう。