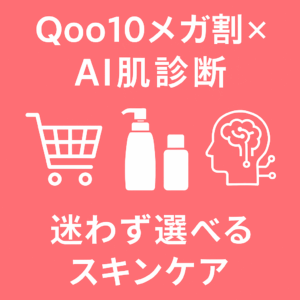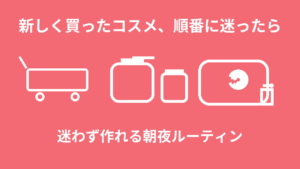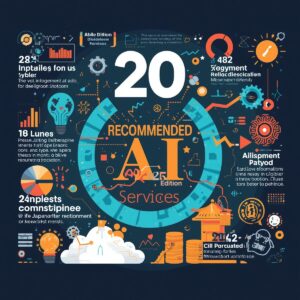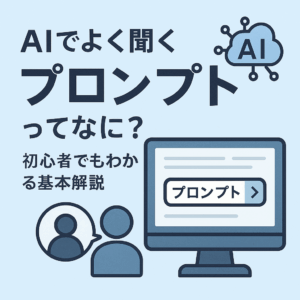朝の通勤電車で「遅延証明書が発行されるのかどうか」「発行されるとしたら何分遅延の証明書なのか」不安になった経験はありませんか?
そのモヤモヤを少しでも解消できないか──。
この記事では、AIによる構想化の試み を通じて浮かび上がった「遅延証明書の発行予測サービス」をご紹介します。
鉄道会社の公式サイトでは運行状況は確認できますが、証明書が発行されるかどうか、そして何分遅延の証明書になるのかは分かりません。本記事はそれを事前に知る仕組みを実現できるかをAIに聞いてみる試みです。
なぜ「何分遅延の証明書になるか」を予測したいのか整理
- 遅刻すると、会社や学校で遅延証明書の提出を求められるケースがある。
- 基本的に遅延証明書はWeb掲載であるが、数時間後までは遅延証明書が準備中表示のケースがある。
- 運行状況はリアルタイム情報しか見れないので、遅延解消後はその時間帯でどれくらい遅延があったかを把握しづらい。
準備中表示
⇒遅延があったとしても実際に遅延証明書が発行されるのか不安になるかも
その時間帯でどれくらい遅延があったか把握できない
⇒発行される遅延証明書の遅延時間が何分と記されているか によって相手に伝わる印象は変わるので、あらかじめ知りたい人もいるかも
AIにサービス構想を考えるプロンプトを投げてみた
※今回はGeminiを利用してます。
プロンプト
電車の遅延証明書について、次のようなサービス構想を考えてください。
- 焦点は「遅延証明書が発行されるのか、発行されるなら何分遅延の証明書になるのか」を事前に把握する仕組み
- 証明書は3〜4時間単位でまとめて発行されるため、その時間帯の最大遅延を基準にする
- AIは開発補助として活用し、将来的にはしきい値の自動最適化も視野に入れる
- 「参考情報」であることを明記するAIからの回答
はい、電車の遅延証明書に関するサービス構想について、承知いたしました。以下に内容をまとめました。
サービス構想:遅延証明書発行予測サービス
このサービスは、電車の遅延証明書が発行されるかどうか、またその遅延時間が何分になるかを事前に予測し、利用者へ提供するものです。
1. サービスの目的と提供価値
多くの鉄道会社では、遅延証明書は30分や60分といった特定の時間単位でまとめて発行されます。そのため、利用者は「自分が乗っていた電車が何分遅れたか」ではなく、「その時間帯の最大遅延」を基準とした証明書を受け取ることになります。
このサービスは、この**「時間帯の最大遅延」を事前に予測**することで、利用者が遅延証明書が必要になるかを判断したり、会社への連絡をよりスムーズに行えるようにすることを目的とします。
2. 予測の仕組み
各路線の運行情報をリアルタイムで収集し、AIモデルを活用して遅延時間を予測します。
- リアルタイムデータ収集:各鉄道会社の運行情報、SNS上のリアルタイムな遅延情報、過去の遅延データなどを収集します。
- AIによる遅延予測:収集したデータを基に、特定の時間帯(例:朝7時〜10時)における最大遅延時間を予測するAIモデルを構築します。このモデルは、運行状況の急変(人身事故、車両故障など)も考慮できるように開発を補助します。
- しきい値の自動最適化:将来的には、予測精度を向上させるため、AIが遅延証明書が発行される基準(例:15分、30分)などのしきい値を自動的に学習・最適化する機能も視野に入れます。
3. 提供情報と表示方法
サービス利用者は、以下の情報を簡単に確認できます。
- 遅延証明書の「発行見込み」:遅延証明書が発行される基準(例:15分以上)を満たすかどうかの見込みを表示します。
- 予測遅延時間:その時間帯に発行される遅延証明書の最大遅延時間(例:「30分以上」)を予測して表示します。
4. 留意事項:参考情報としての提供
このサービスで提供される情報は、あくまでも**予測に基づく「参考情報」**であることを明確に伝えます。
実際の遅延証明書は、各鉄道会社が公式に発行するものです。サービス利用者がこの情報を参考にする際は、最終的な判断は各鉄道会社の公式サイト等で確認するように促します。
このサービス構想について、さらに詳細を知りたい点や、追加で検討したい事項はありますか?
AIに設計をお願いしてみた
構想レベルで終わらせず、もう一歩深掘りするために 設計してもらうためのプロンプトも追加で投げてみました。
プロンプト
上記のサービス構想をもとに、実際に動かす場合の基本設計を考えてください。
- 必要なデータ項目
- 処理フロー(データ取得 → 判定 → 表示)
- 利用者インターフェースのイメージ
- 考慮すべき制約やリスク
AIからの回答
車の遅延証明書発行予測サービスについて、承知いたしました。先のサービス構想をもとに、実際の開発を想定した基本設計を以下にまとめます。
1. 必要なデータ項目
AIモデルの学習とリアルタイム予測に必要なデータは以下の通りです。
- 基本データ:
- 路線名: 東海道線、中央線など
- 区間: 東京〜横浜など
- 日付: 2025/09/05など
- 時刻: 07:30など
- 遅延時間(分): 15分、30分など
- 遅延要因データ:
- 要因カテゴリ: 人身事故、車両故障、信号トラブル、悪天候など
- 詳細情報: 事故発生時刻、復旧時刻など
- 過去の遅延証明書発行データ:
- 発行時間帯: 07:00〜10:00など
- 発行遅延時間: 30分、60分など
- 外部データ:
- 気象データ: 天候、気温、風速など
- イベントデータ: 大規模イベントの開催情報など
2. 処理フロー
システムは「データ取得」「判定・予測」「表示」の3つの主要なフェーズで動きます。
1. データ取得フェーズ
- リアルタイム運行情報: 各鉄道会社の公式サイトやAPIから運行情報をスクレイピングまたはAPI連携で取得します。
- SNS情報: X(旧Twitter)などのSNSから特定のハッシュタグやキーワードを含む投稿を収集し、遅延発生の兆候を検知します。
- 過去データ: 過去の運行実績、気象情報などをデータベースに蓄積します。
2. 判定・予測フェーズ
- AIモデルによる予測: 収集したリアルタイムデータと過去データをAIモデルに入力します。
- モデルA(遅延予測): 過去のデータに基づき、特定の時間帯に何分程度の遅延が発生するかを予測します。
- モデルB(要因分析): リアルタイムの情報(「人身事故」「車両トラブル」などのキーワード)から遅延の主要な要因を分析し、遅延の深刻度を判定します。
- 遅延証明書発行判定: AIモデルの予測結果と、各鉄道会社が定める証明書発行基準(例:15分以上の遅延)を照らし合わせ、「発行見込み」の有無を判定します。
3. 表示フェーズ
- 予測結果をWebサイトやアプリのUIに反映させ、利用者が直感的に理解できるように表示します。
3. 利用者インターフェースのイメージ
Webサイトまたはスマートフォンアプリでの利用を想定します。
- トップ画面:
- 主要な路線(例: JR山手線、東武東上線)の現在時刻における遅延証明書発行見込みをアイコンとテキストでシンプルに表示します。
- 例:「JR東海道線:遅延証明書発行見込み(30分以上)」
- 路線詳細画面:
- 特定の路線を選択すると、時間帯ごとの予測遅延時間をグラフで表示します。
- 例:「7:00〜10:00:予測遅延35分(30分証明書発行見込み)」
- 遅延の要因(例: 人身事故、信号トラブル)や、その発生時刻・復旧見込みなどの詳細情報も表示します。
- 注意事項:
- 画面の目立つ場所に「当サービスは予測に基づく参考情報です。実際の遅延証明書は各鉄道会社の公式サイト等でご確認ください」という注意書きを常に表示します。
4. 考慮すべき制約やリスク
- データ取得の制約:
- 鉄道会社の公式サイトからのデータ取得(スクレイピング)は、サイトの規約変更や技術的な変更により突然利用できなくなるリスクがあります。
- APIの提供がない場合、リアルタイム性の確保が難しくなります。
- 予測精度の限界:
- AIモデルは過去のデータに基づいているため、予測不能な事象(例: 大規模な自然災害、予期せぬ事故)には対応できない可能性があります。
- 予測結果が外れた場合、利用者の信頼を損なうリスクがあります。
- 法的リスク:
- 誤った情報を提供したことにより、利用者に不利益が生じた場合の責任問題が発生する可能性があります。
- 「参考情報」であることを明確に表示し、利用規約で免責事項を定める必要があります。
- インフラコスト:
- 大量のリアルタイムデータを処理するため、サーバーやデータベースの運用コストが高くなる可能性があります。
これらの課題を乗り越えるために、システムの堅牢性向上や、予測精度を継続的に改善していくことが重要です。
まとめ
実現までは遠いですが、「こんなサービスがあったら便利かも」をAIと一緒に形にしてみました。
何かを実現したいというインプットがあれば、AIが実現のためのサポートをしてくれるので是非試してみてくださいね。
★利用するデータなど(今回であれば運行情報などの公開データ)、関連する規約などには注意してくださいね。
補足:前述のサービスアイデアを元に誰かが実装したら嬉しいですし、もしかしたら自分で挑戦してみるかもしれません。